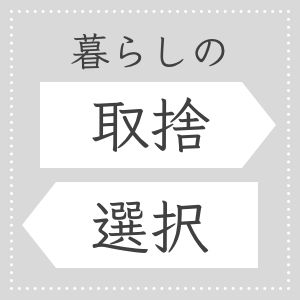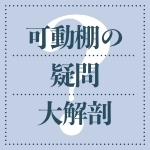今回の「暮らしの取捨選択」に登場するのは、「カゴアミドリ」店主の伊藤朝子さんです。東京・国立と長野・松本に店を構えていましたが、2024年より実店舗は松本に集約。生活の拠点も少しずつ松本に移しています。かごに対する思い、日々の暮らしで大事にしていることについてお話を伺いました。後編はこちら
豊かな国に生まれた人間として、果たすべき責任を実感しています
世界のかごを扱う専門店「カゴアミドリ」は、かご好きには広く知られた名店。伊藤さんが夫婦でこの店を始めたのは、2010年のことです。
「それまでは商社に勤務してODA(政府開発援助)に関わり、その後は国境なき医師団の事務局職員に。特に10年近く勤めた国境なき医師団では、日本の暮らしが世界のスタンダードではないことを知り、大きな衝撃を受けたんです。海外現場からのレポートは、涙なしに読むことはできませんでした」

いかに自分が恵まれていて、便利で幸せな国に住んでいるか。その幸せをただ享受するだけでは、知らず知らずのうちに搾取する側になってしまうと痛感した伊藤さん。夫である征一郎さんとの出会いも、伊藤さんの価値観を大きく変えました。
「アウトドアウェアブランドに勤めていた夫は、自然や環境保護に強い関心を抱いていました。医療や人道支援への意識だけに偏っていた私の視野を、大きく広げてくれたと思います」
結婚前には、山好きの征一郎さんと一緒にアメリカ・アラスカの原野で何日もキャンプしたことも。

「手つかずの自然をそのまま残すため、足跡以外の痕跡を残さないように厳重に管理された国立公園、見渡す限り人工物のないトレイルを何日も歩きました。最小限の食料と寝袋を背負い、水を汲める場所も限られています。私は人間である前に生き物で、生きるとはどういうことなのか。ハードな環境でしたが、生命はこんなふうに維持されているのだと強く実感できました」
30代で学んできたことを、自分たちらしく形にしたい。そのツールとして選んだのが、かごでした
人道支援・環境保護への関心を高め、経験を積んできた30代を経て、伊藤さんは店を開くという新たなチャレンジをスタートさせます。商材としてかごを選んだのは、フェアトレードで途上国の支援ができ、環境に負荷をかけないでつくれるものだから。

「つくり手や生産国を訪ねて回ることで、かごの魅力にどんどんのめり込んでいきました。かごは遥か昔からずっと人の暮らしに寄り添ってきた道具。地域や風土によってかごの材料はさまざまで、文化を映し出す鏡でもあります。その地で採れる材料に合わせて先人たちが創意工夫を凝らし、試行錯誤を繰り返し、用途に合わせて改良を加えてきました」

かごは思った以上に奥が深い、と伊藤さん。何十もの扉があって、開くことで見えてくる世界がたくさんあるといいます。
かごづくりは、現代経済にとり込まれなかった手仕事。かごを取り巻く現状や文化を伝えたい
「カゴアミドリ」で取り扱うかごは、その多くが生産者と直接取引して仕入れたもの。
「できるだけ直接お目にかかって、どんなふうに誰がつくったのかを知りたいと思っています。一対一のお付き合いは個人店だからできることで、私たちの強み。でも、安定した仕入れを行う難しさもあります。産地や使う素材、つくり手さんごとに制作のペースがさまざまだからです」

「一つひとつ手づくりするかごは、ビジネスとして考えると、手間のかかる商材です。過去数十年の経済からはとり残された手仕事だと言えます。職人はどんどん減っているので、残念ながら継承が途絶えてしまったものも。こうした伝統工芸は、一度途絶えてしまうと復活させるのは本当に難しい。誰かがつくっているのを横で見て学ぶのと、手探りで考えながらつくるのには雲泥の差があるとよく聞きます」
いっぽうで最近では、若いつくり手も少しずつ増加。
「単に職業としてだけではなく、自然に寄り添う生き方としてかご職人の道を選ぶ若いつくり手が増えています。変化する時代の中で、新しい価値観でかごづくりと向き合う姿は本当に心強いです」

イタヤカエデやモミジでつくられる木のかご、滋賀の小原かご。最後のつくり手・太々野さんと弟子の荒井さんによってその伝統が守られています。「カゴアミドリ」でも今年から取り扱いを開始

伊藤さんが自宅で7年ほど愛用している、福島・小名浜の「万漁かご」。公私共に親しくしていたつくり手でしたが引退され、同じモノはもう手に入らないそう
自然との向き合い方。季節を読むということ。材料は決して採りすぎず、無駄なく使うこと。技を受け継いでいくこと。これらはすべて、かごのつくり手から伊藤さんが教わったことです。
「私たちの仕事は、素敵なかごをただ販売するだけではないと思っています。その地域に根ざしてきたかご文化を伝えること、つくり手を支えることも大事な要素です」

今回教えてもらったのは……

-
伊藤朝子さん
日本・世界のかごを取り扱うバスケット専門店「カゴアミドリ」を夫とともに営む。かごの産地を訪れ、つくり手を訪ねるのもライフワークのひとつ。長野・松本にある実店舗では企画展や環境にまつわるイベントを定期的に開催している。品揃えが豊富なオンラインショップも好評。