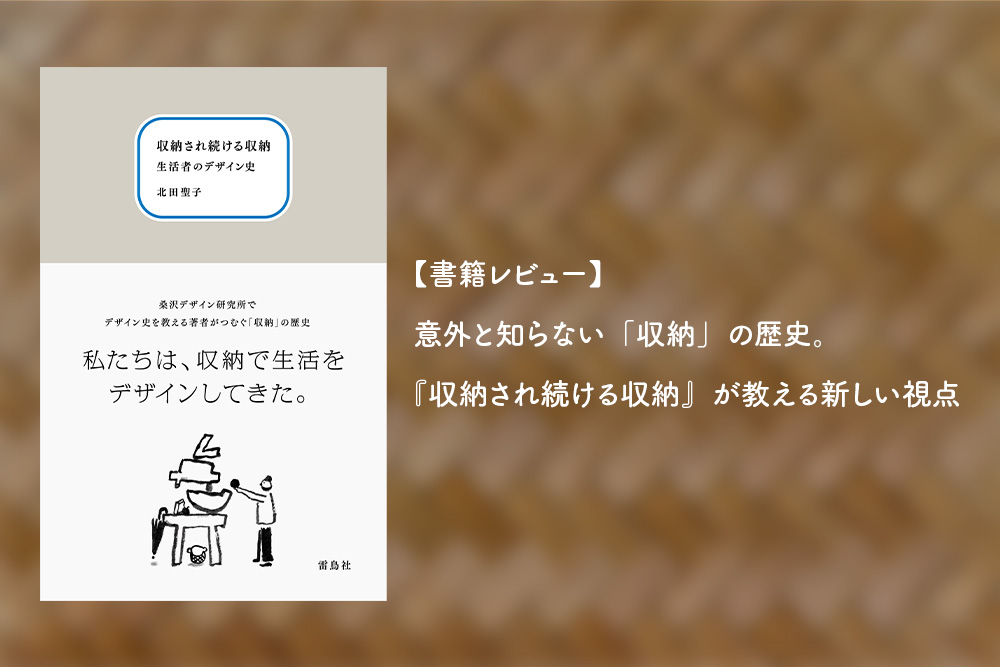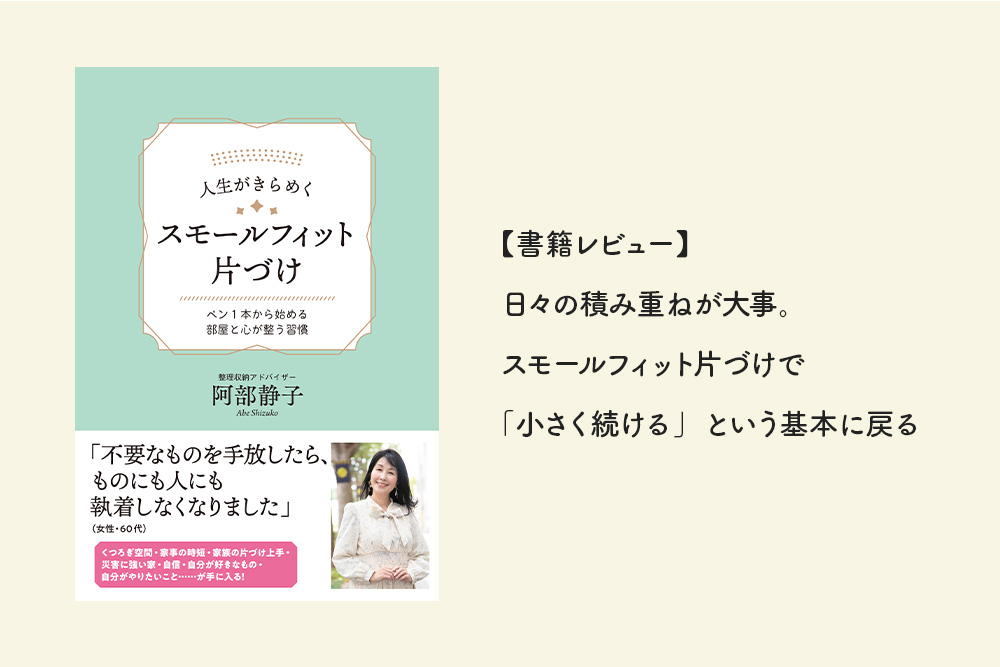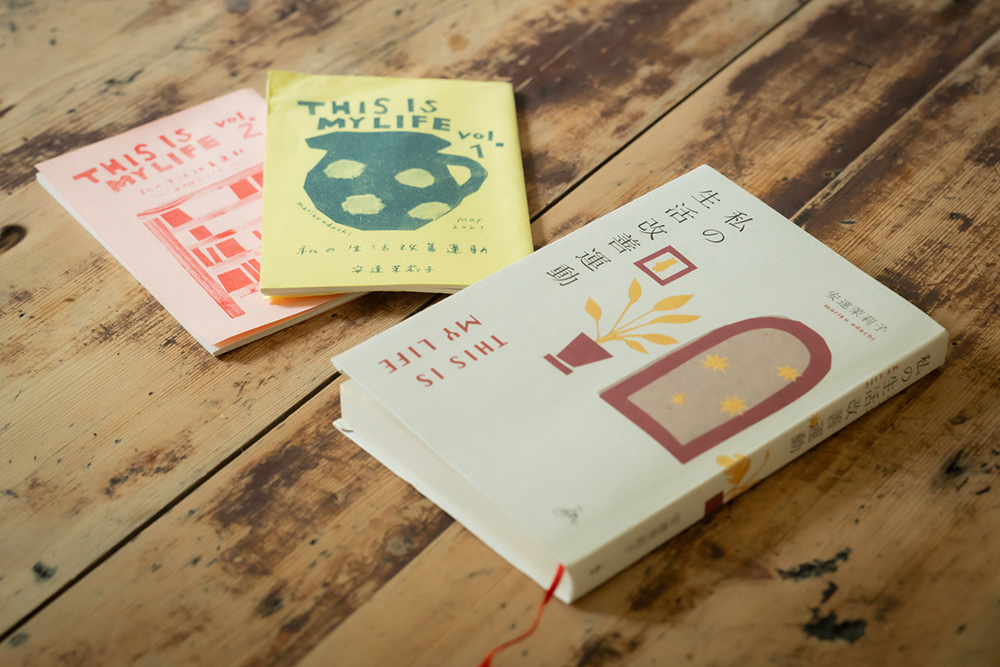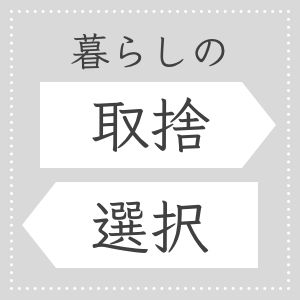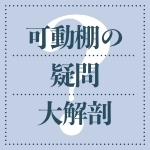HOUSTO編集部が「今、気になる本」をシェアするストレージレビュー。今回は、日々の暮らしに欠かせない「収納」の概念がどのように形づくられてきたのかを紐解く『収納され続ける収納 生活者のデザイン史』を取り上げます。
どんな人が、どんなふうに収納を語ってきたのか
整理収納は、SNSでも話題のトピックとして取り上げられ続けているキーワード。中でも収納について、いつその概念が生まれ、私たちの暮らしにどんなふうに浸透してきたのでしょうか。そんな疑問に向き合ってくれる本を見つけました。
『収納され続ける収納 生活者のデザイン史』の著者は、北田聖子さん。専門学校桑沢デザイン研究所で、デザイン史などの授業を担当しています。
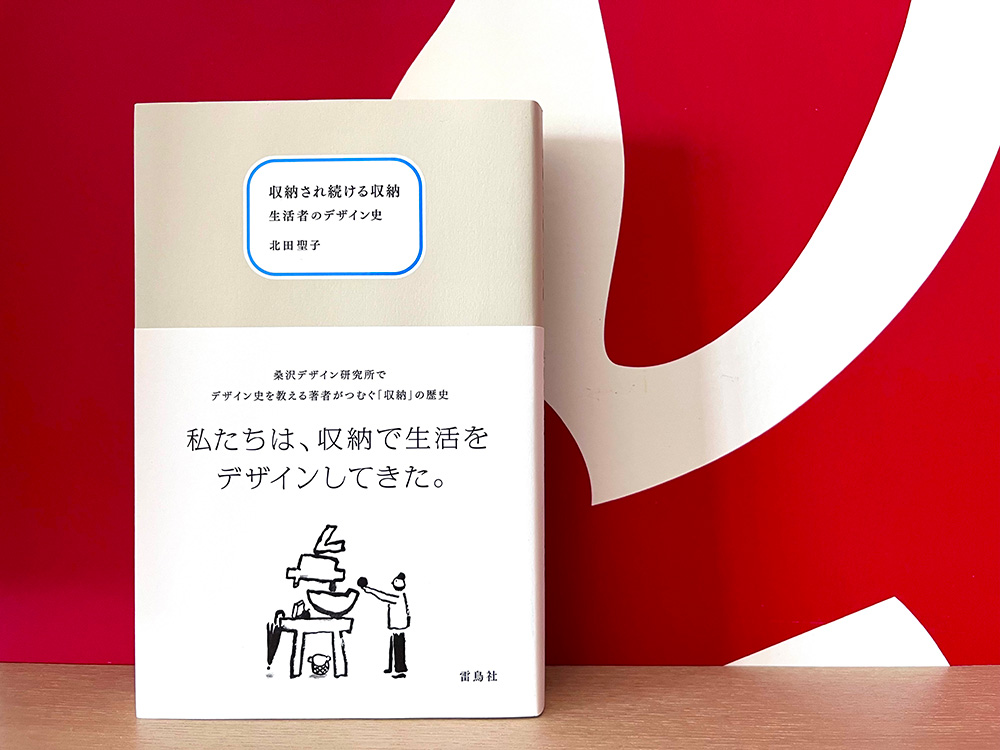
近代において、収納がどのようにメディアに取り上げられ、語られてきたのかをていねいに分析し、綴った内容です。
本書では時代を追ってさまざまな人物の収納への関わりが紹介されています。まずお伝えしたいのは、執筆にあたって参照された膨大な参考文献の数。それは明治期に創刊した婦人雑誌『婦人之友』から始まっています。戦中、戦後、高度経済成長期の考察を経て、今でも活躍中の住まい方アドバイザー近藤典子さん、HOUSTOでもおなじみの整理収納コンサルタント本多さおりさん、『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』で話題となったミニマリストの佐々木典士さんの名前も登場。参考文献もブログや書籍、ウェブサイトまで多岐にわたります。
行李にラベリング!? 「収納」という概念は明治時代からあった
本書は収納の歴史を「2000年代」「戦後から90年代」「明治後期から戦中」時代ごとに大きく分類。
こうして100年単位の大きな枠組みでとらえると、どの時代も収納が社会の変化を映し出していることがよく分かります。
たとえば、明治は洋風文化が一般庶民にも浸透しつつあった時代。和洋のアイテムが混在し、急に家のモノが増えたことで生じた暮らしの悩みを収納テクニックで解決しようとしています。1980年代にはティーン向けのインテリア雑誌の創刊が相次ぎ、団塊ジュニア世代や第二次ベビーブーム世代(当時は中学生から高校生)が自分の部屋(もしくはスペース)を素敵に整えるための特集が多数登場。
明治時代の雑誌に住まいでモノをしまうことの意味での「収納」という言葉自体は使われていないようですが、「物のしまい方」「おさめ方」「かたづけ方」として特集が組まれることがあったと北田さんは言います。
押入れというスペースをどのように効率よく使うか、雑誌に掲載された理想の収納イラストも本書では紹介。押入れを使いやすく仕切ったり、柳行李に札をつけたり(まさにラベリング!)、今も続く収納のテクニックがすでに取り入れられていました。
現代の団地暮らしの収納術に見られる工夫が、明治時代にも既に存在していたことには強く驚かされます。私たちは、形を変えながらも同じような課題に繰り返し向き合っているのかもしれません。ちなみに、誌面上に図解(イラスト)として登場する行李が誌上販売されていたというエピソードには、当時の商魂の逞しさを感じずにはいられません。
平和に暮らせているからこそ、収納のことを語れるのかもしれない
同じように回帰しなければいいな、と考えさせられながら読んだのが、戦中の収納について触れたパートです。
戦時中、雑誌では戦時体制への協力を読者(国民)に呼びかける目的で収納が語られていました。
モノは空襲からの避難や出動命令で持ち出すことを前提に収納。防空壕の側壁をくり抜き、棚をつくって生活の場所にする。そしてとにかく簡素であることが美であり、持ち物をなるべく少なくする実践例が取り上げられていたと北田さんは語ります。
現代のミニマリズムは「持ちすぎたモノを手放してこそ自分軸が見えてくる」という、個々の生き方の問題にも通ずるところがありますが、この時代は違う。モノを持たないことは同じでも、そうせざるを得なかった社会状況と価値観の強要があったと容易に推測できます。
収納は、「生活」が続き、日常が繰り返されるという前提があるからこそ成立するのではないでしょうか。繰り返されるからこそ、次に使うときのことを考えて、物の置き場所を一定にする、物を出し入れしやすい位置にしまうということが行われるはずです。(中略)収納は、明日があると信じることから実践されるものなのかもしれません。
北田さんのこの言葉に、すべてが詰まっているような気がします。何を持つのか、何をどう収納するのか自由に選べる幸せをまずかみしめたい。そんなことを考えさせられた一冊となりました。
書籍情報
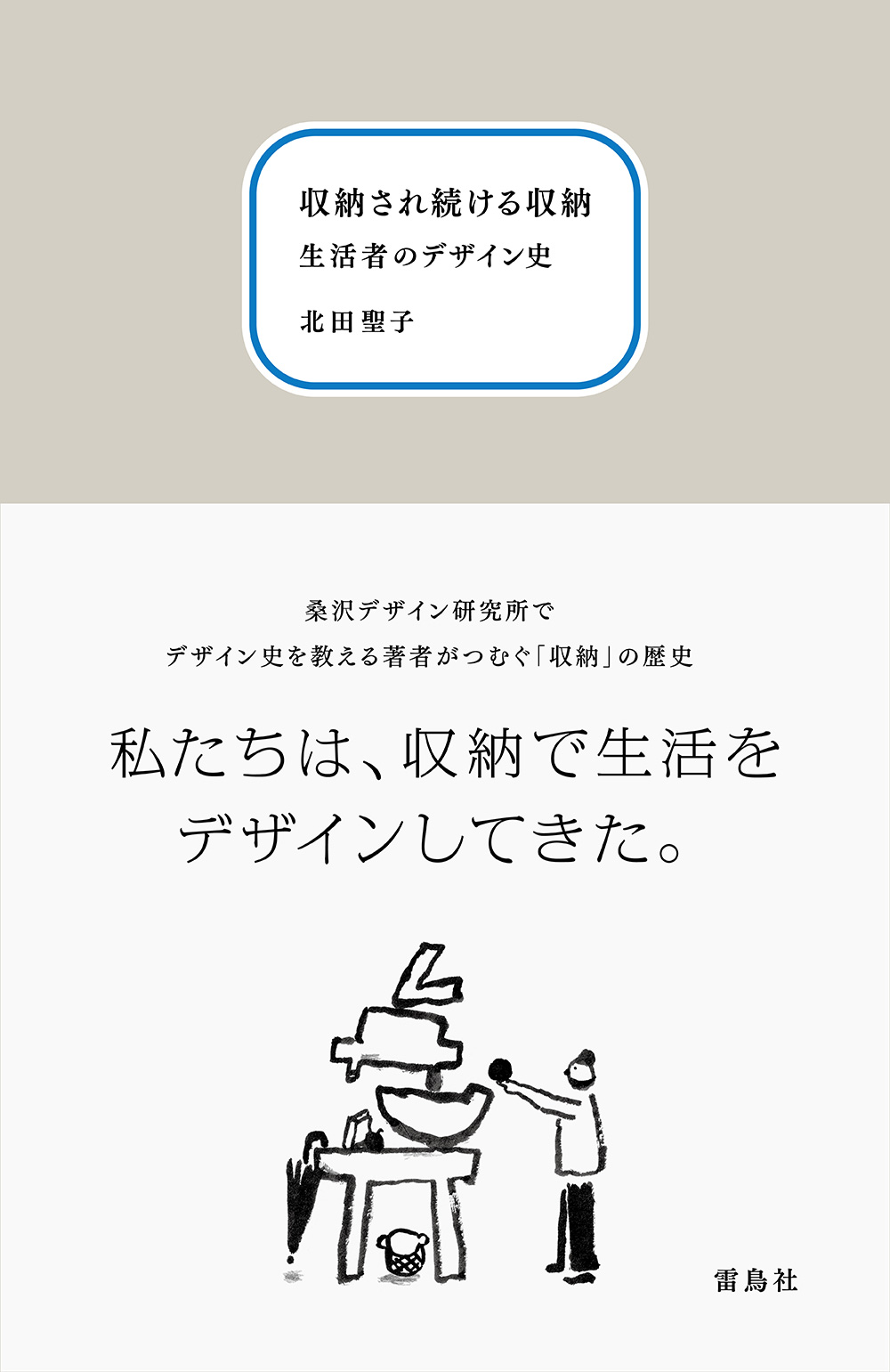
収納され続ける収納 生活者のデザイン史
北田聖子著
雷鳥社
https://www.raichosha.co.jp/book/251