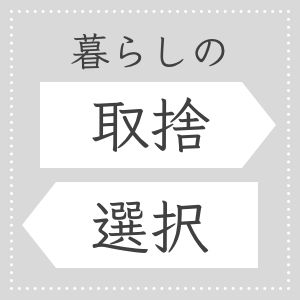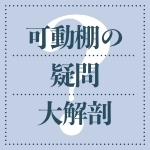片付いた使いやすい部屋への意識が高く、整理収納アドバイザーの資格を持っている小竹さん(仮名)。フルリノベーションをした際には、知識を活かしてリビングにオープンな可動棚を設置しました。さすが、とても美しい棚の景観! パッと見、とても悩みがあるとは思えません。しかし、小竹さんは悩みがあるのだそう。このように、素敵なインテリアのお住まいでも、実は「なんだかしっくりこない」という方は多いのではないでしょうか。今回は、その原因と解決法を探ります!
今回の収納迷子さん

小竹さん(仮名)
・78㎡のマンションに2012年入居
・夫婦ともに在宅勤務が増え、2023年に2LDK→3LDKにフルリノベーション
・夫、娘(小3)、息子(年長)との4人+ワンちゃん1匹でお住まい
・週に数日在宅勤務をするワーママ
お悩みは、「床置き」「雑然感」

ダイニングの壁一面に設えたオープンな可動棚。
リビングダイニングに備え付けの収納はここだけのため、様々なモノがここに集まってきます。十二分に美しく、使いやすそうではあるのですが……。
本当は床にモノを直置きしたくない

「以前は床置きがなかったのですが、ランドセルのためのスペースをつくったところモノが押し出されて床面へ。できればすべてのモノを棚の上に戻して、床を掃除しやすくスッキリと保ちたい。将来的にはルンバの導入を希望です。」(小竹さん)
見えづらいけど、実はコードがぐちゃぐちゃなのもモヤっとポイント

こどもたちの使うデバイスの定位置。こどもの席からすぐ近くではあるものの、イスから降りて振り返らないと出し入れできません。時折、ダイニングテーブルの上にデバイスが出しっぱなしということも……。「充電コードが複数本伸びて、コードが絡まってしまうのも、なんとかしたい」(小竹さん)
収納用品選びが難しい!

モノの取捨選択を繰り返し、物量はだいぶ減らしたのに雑然感がぬぐえない……。
また、棚板の奥行きが深くて収納用品が奥まってしまうのも悩みです。
今回の改善ポイントは「モノ」「収納用品」「動線」を丁寧に繋ぐこと

一番気になったのは、モノと収納用品の不一致です。たとえばこどものハンカチが、「二段階に開けて取る」「手前に雪崩れて来そうで気を遣う」仕組みのボックスに入っていたりする。一つひとつのモノと向き合い、適した収納用品に見直していきましょう。
また「別の場所で飲む薬がこちらにある」など動線と定位置の不適合も見られます。
「モノ」「収納用品」「使う場所」を丁寧に合わせていくことが、今回のポイントになりそうです。
その際、オープン棚であることを考えてデザイン面も重要視したいところ。
そして
〇床置きをやめ、できれば最上段も少し下げて「床」「天井」が端まで見えるようにする。圧迫感をなくし、部屋を広く見せられたらベスト。
〇収納用品はなるべく少ない種類にしてスッキリとした見た目にする。
〇とくにこどものモノは取りやすくする。
といったポイントで改善をしていきます!
まずは全部出し。これが一番簡単な道だから

オープン棚からすべてのモノを出します。
大変なようでも、モノの量や内容を把握し、先入観に囚われることなく再構築するための最も簡単な方法です。
すでに物量を減らし、きれいに分類され、収納用品にまとめられている小竹さんの棚は全部出しもあっという間!
「片付いている→ラクに改善できる→さらに片付く」の好循環。
一度でうまくいかなかったとしても、手をつけることにはプラスしかありません。

そんな小竹さんでも、出してみると意外なほどの量!
動かしてこその可動棚

全部出し終了!
こちらの可動棚は、縦に3スパンあり、細かく動かせるようになっています。棚板3枚を真横に並べれば、端から端までの長い1段に。
しっかりと重量のある棚板なので、動かすにはコツと力が必要。
それでも普段の使いやすさのために、数センチでも動かしてあれこれ試していきます。
まずは、こどもの「ランドセル置き場」を最優先に

小さいこどもの「使いやすい」の範囲は非常に限られるため、最初に決めて位置取りしていきます。実物は登校中なので、「ランドセル」と書いたコピー用紙を置いてシミュレーション。もうすぐランドセルがやってくる年長の弟くんの分も位置取りします。
その隣には姉弟の上着や帽子、習い事用品をざっくり放り込める大きめの布ボックス。引き出しには細かいモノを分類して、出し入れがしやすい仕組みをつくりました。
この際、この段の上の棚板をぐっと上げました。背中からランドセルを下ろしやすいよう、ふたを開けやすいよう。こどもの収納からはとくに「~しにくい」を排除します。

習い事の道具など、置き場所に困るモノはすべてここへ入れておけばOK。
散らかりと探しものを防ぎます。

引き出しの最下段は姉弟それぞれのお菓子ボックスに。真ん中は通信教育のおまけなど雑貨、最上段にはハンカチを入れました。

薄い引き出しは、細かいモノを埋もれさせず、奥まで選びやすくしてくれる優れた収納。何があるかを一覧できて、持っているモノをきちんと活かせます。
左の列はお姉ちゃんの引き出し。右列は弟くんの引き出し。弟君のハンカチと靴下は別の部屋にあったのですが、この引き出しに移動させました。
「最近怖がりで、靴下など取りに行くとき向こうの部屋についていくのが面倒だったのでこれでラクになりそうです!」と小竹さん。
収納を全体的に見たときに、同じ収納用品を複数個並べると秩序が生まれてスッキリ見える効果があります。
そんなデザインの観点から並べてみた引き出しですが、弟君の靴下ハンカチをこちらに持ってくるのは「引き出しを置いてみたから」生まれたアイデアでした。
アルバム、絵本を「本系のモノ」としてまとめる

こどもたちの写真を印刷し、アルバムを作り続けている小竹さん。なかなかの量が貯まってきました。こどもたちの絵本に加え、大人の本も合わせると結構な量があります。
絵本は、今までは布ボックスに入れて床置きされていたのですが、「床置き」と「こどもの目に入らない」ことで、なかなか広げられない状態でした。せっかく持っている本なら、読む機会が多い方がいい。
というわけで、アルバムと本を同じゾーンにまとめて「本系のモノ」とひとくくりに。背表紙はカラフルで情報量としては大きくなりますが、「本系」でまとめたことでひとつのカタマリに見せる効果があります。
これが、大人の本は上、アルバムはその下、絵本はさらに下など散っていると、情報量もだいぶ増加するので、あえて同じ段に配置しました。

絵本もアルバムも、見る機会があってこそ存在に価値が。見やすく並んでいるのが一番です。こどもには少し高い位置ですが、ここにあるのは2軍絵本なのでOK。必要を訴えられたら1軍の場所に昇格させます。
「チーム」をつくって見た目を揃える

あちらこちらに散っていたラタンのかごを、集合させて配置。
ひとつのカゴで視覚情報1ではなく、チームとして1にします。この配置の仕方を意識すると、収納全体に秩序と静けさがもたらされます。
今回も、ほかの部屋で使われていた同じ収納用品を見つけてきて使いました。まったく同じ収納用品がなかったとしても、半透明、白といった色味、ラタンや布といった素材を合わせて並べて置いてみてください。

ラタンのかごは「診察券やマスクといった通院セット」「裁縫セット」「よく使う文具」などをまとめて。フタがなくても重ねられるのが嬉しい、その名も「重なるラタンボックス」(無印良品)。よく使うモノを上段にします。

アルバム以外の紙類は、ファイルボックスで分類収納。色をそろえるために、ほかの部屋で使われているファイルボックスをこちらへ移設しました。
縦書きのラベリングがおしゃれです。
最上段「布ボックス」チームには思い出系と、頻度の低い習い事の道具を。高いところなので軽い布製が向いています。下の方をつまんだりできるのもいい。
黒いボックスは、左が「工具やテープ類の入ったホームセンター系」、右が「コードやデジカメといった電気屋系」。系統立てて、まとめています。

こちらの布ボックスは、かさばる「ワンちゃんのペットシーツやおやつ」「ティッシュ系ストック」。下段のこどもの布ボックスとチームに見せています。

ボックスが奥まらないように、後ろにファイルボックスを入れ、棚の奥行きを活用しています。ファイルボックスの中身は、保管系の書類、出番のない思い出のモノなど普段出し入れのないモノ。
スッキリ見えのポイントは、前面が揃っていること。奥行きが合わないボックス同士を並べる時は、後ろに二軍以下のモノを支えとして置くことで、奥行きをそろえます。
今回の発掘アイテム「こどもアイテムまとめワゴン」

別室で使っていたワゴンを、オープン棚とダイニングテーブルの間に移設。これまでこどものデバイスはオープン棚に置かれていたため、コードがコンセントまで伸びて絡まっていました。ワゴンをコンセントの前に置けば、コードが伸びず見た目もスッキリ。位置がこどもの席の真横なので「こどもアイテム」を入れれば着席したままモノを出し入れできます。
一石二鳥のワゴンづかい! 上の段からデバイス、ドリル、「スチールタップ収納箱・フラップ式(無印良品)」に電源タップを入れて。
完成!BEFORE-AFTER
Before

After

意識して変えたポイントはこちら。
〇床置きをやめ、最上段の棚板を下げ、床と天井が隅まで見えるように=圧迫感を減らし、部屋を広く見せる効果が!
〇同じ収納用品をかため、グループでひとつの視覚情報とする=ごちゃつきを抑え、スッキリ感を底上げできる
〇見たい、読みたいモノは選びやすいように、手に取りやすい位置に設置
〇ほぼ出し入れのない保管系のモノを棚の奥に置き、いつも使うボックスが奥まることなく前面がそろうように設置
〇BEFOREに写っている6つの小引き出し(中央・木製)にはこどもの薬などが。飲むところから離れているので、リビングの別の場所へと移設
〇最上段に空間を設け、ひな人形や五月人形を飾るスペースに。スポットライトの向きを変えて、飾りに光が当たるよう調整すると、素敵なディスプレイスペースが出現!

「こどもがここから本を選んだり、もうこれはいらないと判断してくれるようになりました!」「掃除しやすくなり、さらに空いた床面が犬のお気に入りの場所になりました。クッションを置いてあげようかな」「息子の靴下とハンカチがこちらに来て、本人も大喜びでした」と小竹さん
収納上級者の方、「なんだかしっくりこないなあ」というときはとにかくあれこれ試してみよう!
小竹さんのお宅は「無印良品」の収納用品が各所で豊富に使われていたため「ラタンがいいかな」「布の方が便利だな」とあれこれ試すことができました。「無印良品」の収納はそれぞれ機能や見た目がいいのはもちろん、モジュールや雰囲気が統一されているのでさまざまに組み合わせられてどこにでも使える、可能性の果てしない収納用品だと再認識。
また可動棚を細かく調整することで、モノと取りやすさに合わせてベストな位置を探ることができました。可動棚のよさもまた、とくと実感したBEFORE-AFTERとなりました。
家族みんなで使う収納を考えるときは、“お片付け弱者ファースト”が基本です。こどもを優先に、こども目線での取りやすさ、わかりやすさから考えます。こどもは今どんなことができているか、何ができないかを観察し、難易度はできるだけ下げることが成功の秘訣です。あまり細かくさまざまな収納用品に分かれているより、ざっくりとシンプルがわかりやすい。
開けやすい、入れやすい、わかりやすいと「優しい収納」にフルに振って、余ったところを大人のモノで埋めていきました。
もちろん、優しさに振ったところでうまくいくとは限りません。「それならこうしたらどうだろう」を繰り返して、親子の平和共存を探り続けてみてください。