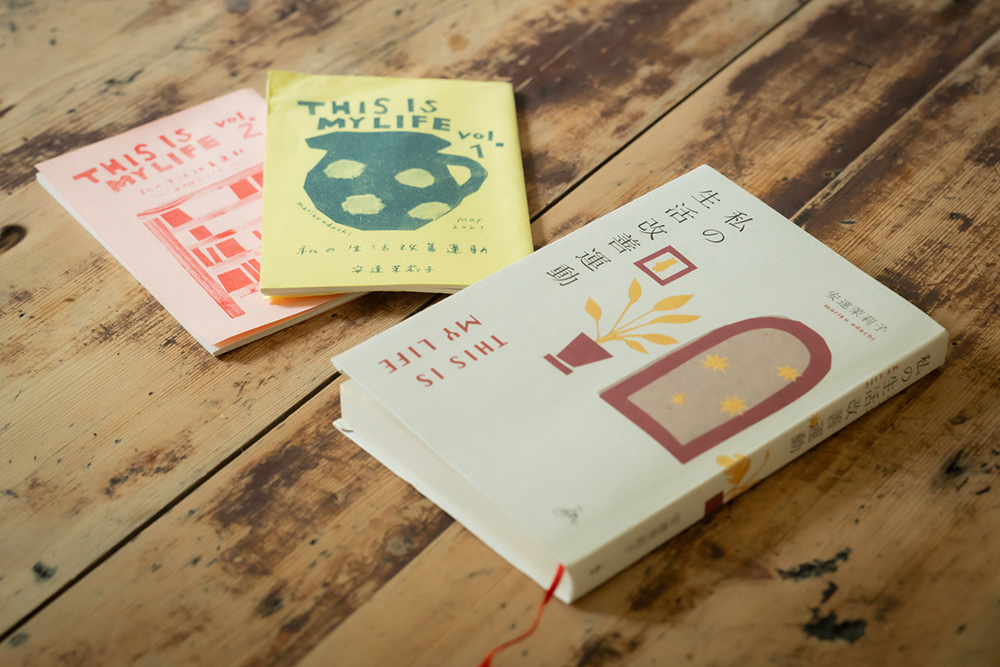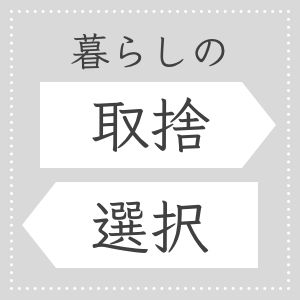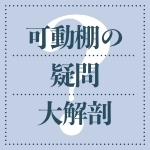文筆家、塩谷舞さんが綴る「もの」のものがたり。一点のものを見つめることから奥行きを持って立ち上がる、文化と想いを語っていただきます。今月はお気に入りの箸から始まり、食具と食文化に広がります。
新しい箸、とはいえ愛用品を新調
新年に箸を買い替える、という人も多いのだろうか。なにも今使っているものが傷んでいなければわざわざ買い替える必要もないとは思うのだけれど、うちのはそろそろ頃合いかな、と先日あたらしい箸を買ってきた。とはいえ、過去6年くらいは買い替えながらも使い続けている同じものだ。
ただの竹箸やないか、と侮ることなかれ。むしろ、竹箸だからこそ成せる機能性の高さが詰まっているのだ。
まずはなんといっても箸先の細さ。塗装がないことも手伝い、限りなく細い。小さく砕けた米粒であれ、器の側面にくっついた鰹節であれ、ひょいと持ち上げられて気持ちがいい。その細さはナイフとしても優秀で、豆腐なども一口大に切って口に運ぶことができる。口の中でも主張は限りなく控えめなので、繊細な味付けを邪魔しない。
箸先は細いが、持ち手は握りやすい太さなのもありがたい。丸いので、どの角度で持ってもしっくり手に馴染む。丸い箸は転がりやすいのが難点だけれど、これは箸頭が平らになっているし、一片だけ竹の皮が残されていてストッパーとしての役割も果たすから、コロコロと転がり落ちることもない。無塗装だから手からつるりと滑ることもないし、カチャカチャとした音も出ない。

さらに長さが25センチあるので、少し手の角度を変えるだけで目当ての皿に、そして口元にまで難なく料理を運んでやることができる。
私は落ち着きのない人間なので、箸をぶっ飛ばすことが度々あったのだけれど、この竹箸を使うようになってからそうした粗相が激減! 良いデザインは、それを使う側の欠点までも補ってくれるのである。
置きやすさと安定感に優れた箸置きを

加えて、これらの箸置きも我が家の食事には欠かせない。いや、かつては「箸置きなんて、丁寧なくらしを演出するための小道具やろ」というくらいには軽視していたのだけれど……使い勝手の良い箸置きに出合ってからはすっかり必需品になってしまった。

こちらは、「FUTAGAMI」のもの。いただきものなのだけれど、使ってみたらその機能性の高さに驚いた。尾根が半円状にくびれているので、どこに箸を雑に置いても然るべき場所にしっかりおさまるのだ。素材は真鍮で重さがあり、底面積も広いので、箸を置いたときにズレてしまうこともない。さらに箸と箸置きが接する面積が小さいので、箸先の汚れも付着しにくい。

お次は、銀座の箸専門店「夏野」のオリジナル箸置き。FUTAGAMIと同じ真鍮製だけれど、さらにシンプルな姿形なので、より日常に馴染みやすい。ただ箸と接する面積が少し広いので、使い始めはちょっとした汚れが目に付くかもしれないけれど、しばらく使っているうちに真鍮に風合いが出てくるので気にならなくなる。同じ形状でアルミ素材の箸置きもあるけれど、重さがある真鍮のほうが安定感は勝る、はず。

このミニマルな箸置きは、「kuros’」というお店のオリジナル。新潟県の燕三条で作られているステンレス製で、シンプルな黒い箸が実に似合う。
私が日々愛用しているのは上述した細竹箸で家には何膳もあるのだけれど、そうした無塗装の箸を客人に出すのもよろしくない。ということで、より清潔に保てる漆塗りのこちらが来客用として活躍している。「THE」というブランドの箸、その名も「THE 箸」である。
漆の口当たりはなめらかで、食事の格を引き上げてくれる。先の一品ほどではないけれど、箸先も細く軽いので、なかなか使いやすい箸だ(手の大きな人には持ち手が細すぎるかもしれないけれど)。
大皿料理は太箸で大胆に
……と、ここまで細い箸先こそが正義、という具合に熱弁してきてしまったが、もちろんこうした箸が不便なときもある。たとえば、青椒肉絲なんかを口いっぱいに頬張りたいときに皿から口へ運ぼうとしても、細い箸ではその隙間から肉やピーマンがバラバラと落ちていってしまうのだ。
それもそのはず。こうした先の細い箸は元来、焼き魚などが多い和食に最適化したもので、大皿料理を基本とした中国の箸はもっとずっと太いのだ。中国の箸はトングのような力強さで、料理をワシッと掴んでたくさん口まで運べ、たちまち口いっぱいに幸せが駆け巡るのだ。日本の細い箸でチマチマと食べるよりも、ずっと美味い!

さらに中国では、大皿に乗った料理を自らの箸で掴み、客人の皿にそのまま取り分けてあげるのが親愛の証。だから箸の長さも日本のそれと比べると随分長い。一方日本だと、良かれと思って箸の上下をひっくりかえして大皿料理を取り分ける「逆さ箸」をする人もいるが、あれは中国では「どんなものを使ってでも食べようとする卑しい姿」とされて、かなりのマナー違反と見做されるらしい。もっとも、口よりも手のほうが細菌が多いので、逆さ箸はむしろ不衛生であるのだし、日本でも勧められた行為ではないのだけれど。
赤い韓国料理に適った金属製のカトラリー
そうした「中華料理」と「細い箸」の取り合わせの悪さに次いで、「韓国料理」と「無塗装の箸」の相性の悪さもなかなかなものである。もちろん、キムチやコチジャンで箸先が真っ赤に染まってしまうからだ。
木材資源が日本ほど豊富ではなく、さらに高麗時代から金属加工技術が発達していた朝鮮では、古くから箸も金属製。かつては毒が入っていないかを確認するために銀のカトラリーが使われたという歴史もあるが、現代でも金属製のカトラリーが愛されている。箸は「チョッカラ」スプーンは「スッカラ」と呼ばれていて、必ず2つセットで使われる。

うちには韓国の小さな石鍋がひとつ、真鍮の古いスッカラが大小4つあるのだけれど、そうした食具でいただく韓国料理は非常に理にかなっている。石鍋でスンドゥブチゲなどを作ったときには、このスッカラが大いに役立つのだ。

スッカラは一般的なスプーンよりも平たい作りなので、一度に掬えるスープの量は少ないのだけれど、豆腐を崩してスープと一緒に口に運ぶには最適だ。さらに本領を発揮するのは食べ終わり。熱々の石鍋を持ち上げ、味噌汁椀のように直接口につけてスープを飲み干す……だなんて絶対に不可能だけれど、スッカラであれば底に溜まったスープも上手に掬うことができるのだ。
中国の太く長い箸も、韓国のチョッカラ&スッカラも、料理店などで出てくると最初は「使いづらいな?」と感じるものの、使い方のコツさえ掴めばむしろ、隣国の味を本当の意味で味わうことが叶う。ただやっぱり、焼き魚定食などを美味しくいただくには、日本の細い箸が一番だ。
西洋の焼き魚はナイフ&フォークで
しかし同じ焼き魚でも調理法を変えれば、箸などいらぬ! というケースも出てくる。
お箸の文化圏を飛び出してポルトガルまで大移動すると、オリーブオイルを塗ったイワシをオーブンで焼き、同じくオーブンで焼いたパプリカやポテト、さらにスライスオニオンと刻んだトマトなど共に、オリーブオイルと塩、レモン果汁などをかけて食べる料理がある。

私はハーブや青唐辛子のピクルスなども乗せて、ホワイトビネガーをかけて食べるのが大好き!
焼きオイルサーディン、といった具合の料理なのだけれど、これを細い箸でチマチマ食べていたのではその醍醐味は味わえない。ナイフとフォークで、皿の上にあるもの全部ゴチャ混ぜにして食べるのが最高に美味いのだ!

ゴチャ混ぜ失敬。
イワシの肝も身も骨もぐちゃぐちゃにして、野菜やハーブと共に口に運ぶ。そうした様々な要素が口の中に飛び込んできたときの楽しさといったら! 箸で丁寧に身をほぐしていたのでは、こうしたカオティックな味わいには到達できない。
ただ「焼き魚はお箸で綺麗に食べなさい」という教育を受けてきたからこそ、こうした食べ方は少し悪いことをしているような気持ちになり、それがかえってドキドキとした高揚感にも繋がる。なによりナイフとフォークというのはその歴史を辿れば、獲物を捉え、その肉を切り分けるための道具でもあったのだ。食べながらアグレッシブな気持ちになるのはそうした歴史も関係しているんじゃないかしら。
これはなにも、箸文化圏が上品で……と主張したい訳ではない。日本では市民権を得ている食べ方も、文化が変わればマナー違反になるのだし。
ヨーロッパから友人夫妻が日本に来た折に一緒に蕎麦屋に行ったのだけれど、「ここでは器を持ち上げ、make noiseしながら食べるのがお作法だからね。Like this!!」とズズズ、と啜って見せた。すると上品な友人はニヤリと笑って、同じくズズズと麺を啜る。そのときの楽しそうな顔といったら!
きっと彼ら彼女らは幼い頃から「音を立てちゃだめ!」という教育を受けてきたからこそ、合法的にルールを破れる異国での食文化に触れて楽しくなっちゃったんだろう。異文化の中に身をおいて、自らの守ってきたマナーを破る瞬間は、ときにエキサイティングなものだ。
……と、お気に入りの箸から出発し、随分と遠いところまで来てしまった。こうした食具ひとつ取っても、そこから広がる文化はあまりに深く広く、発見に満ちているものだ。この連載では月に1度、こうして身近な生活道具を取り上げながら、さまざまな文化のつまみ食いをしていく予定だ。次の更新は2月。みなさま、良い年の瀬を!