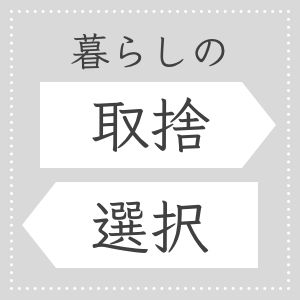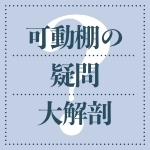「料理ができる子に育ってほしい」と思いつつ、忙しい毎日の中では、つい親がすべてをやってしまうことも……。食事を作る能力だけではなく、「生きる力」や「自己肯定感」を育むなど、料理のスキルには、こどもたちの将来にたくさんのメリットがあります。神戸で人気の料理教室を営むkayoさんに、こどもと料理を楽しむコツ、キッチンの工夫、料理好きに育てるための考え方まで、たっぷりと教えてもらいました。
今回教えてくれたのは…
Kayoさん。料理家、発酵食のエキスパート。「ちょっと可愛い発酵食のお教室 toitoitoi」「もぐもぐ研究所」主宰。食育インストラクター、幼児食アドバイザー。自宅で週3〜4回料理教室を開催。オンラインレッスンも取り入れている。こどもは女の子が2人。
https://www.instagram.com/toitoitoi_ring
こどもたちはキッチンが大好き!

神戸市在住のkayoさんは、長女の誕生を機に自宅でベビーマッサージの教室をスタート。受講者にふるまっていた手づくりおやつが好評だったことから、食育と幼児食を学ぶようになったそう。さらに大学に通い、発酵食エキスパートの資格も取得。現在は発酵食に特化した料理教室を主宰し、一般レッスンから幼いこどもを連れたママたちのレッスン、こども向けのレッスンなど、さまざまなレッスンを開講しています。
住まいは、11年前に新築で購入した3LDKのマンション。kayoさんのインスタグラムには、おいしそうな季節のメニューの合間に、こどもたちのかわいい姿がちらほら……。シンプルに片づいたキッチンと、こだわりを感じるダイニングの様子も見ることができます。
「もともと、私はモノをあまり増やすのが好きではないんです。自分のこどもにも、あまりおもちゃを買いませんでした。ままごとキッチンと、あとは絵本くらい。なければないで、こどもたちはほかに楽しみを見出すんですよね。教室に来てくれる小さなお子さんにも、料理に興味を持ってもらえるように、小さなお鍋とか、野菜のおもちゃとか、そういうものをいくつかそろえています」
手づくりフェルトのおもちゃで、野菜に興味を持たせる

「こども(未就学児)を対象にした料理教室をするときには、まず、フェルトで作ったおもちゃの野菜を使って、『この野菜は、切ったらこんな色、こんな形だよ』などと言いながら、なんとなく興味を引くように。これらはみんな私の母が作ってくれたんですけど、なかなかよくできていますよね」

「こどもの集中力って、そんなにもたないので、まずはちょっと遊ぶ感覚で、そこから実際に野菜を切ってもらったり、飾りつけを楽しんでもらう。好き嫌いをなくしてくれるといいなという思いから、基本的に野菜料理を教えています。硬い野菜、お芋やにんじんなどは事前に蒸して柔らかくしておきます」
こどもにもあえて、本格的な道具、食器を使ってもらう

「自宅でこどもが使う食器は、プラスチックのものではなく、ガラスや陶器を使っています。多少割れることもありますが、それも勉強。こどもたちって意外と注意深いので、今までそんなに大惨事になったことはないですね」
レッスンでは、「台所育児」のこども向け包丁を用意。きちんと見守りながら、順番に調理してもらっているそう。
「調理器具も、あまり切れない包丁は使いません。こどもたちにも料理をしている実感が湧きづらいですし、いつまでも包丁の使い方を学べず、逆に危ないと思うので」
こどもたちに人気のメニューはどんなものなのでしょうか?
「野菜カレーや、動物を形どったパンなどが人気です。ちょっとキャラっぽくするだけでこどもたちは喜ぶんですよ。カレーはごはんを動物の形に盛り付けて、周りにカレーのルーをかけて。のりや野菜で顔を描く。おうちで毎日そういうことをするのは大変だと思いますが、誕生日などの記念日には、親子で料理してみると、思い出に残りますし、こどもたちもペロリと食べてくれると思います」

割れたものは金継ぎをして修理することもあるそう。モノを大切にする心もこどもたちに伝えています。
こどもを料理好きにするために親ができること

さすが、料理家の娘。二人とも、すでに料理上手だというから驚きです。
「上の娘(小6)は、野菜を切ったり、お出汁を取ったりと、小学校に入る前の段階で、一通りのことはできるようになっていました。下の娘(5歳)も、卵焼きは作れます」
娘さんたちは料理の後の片づけまで、きちんとこなすのでしょうか?
「片づけについては、まだそこまで完璧を求めていないんです。大人は片づけを挟みながら料理ができますが、こどもって、集中し始めたらずっと料理を続けたいんですよね。料理を楽しんでもらいたいから、まずはそちらを優先。
一つ教えているとしたら、順番です。ひとつのボウルで何かを混ぜた後、そのまま洗わずに次のものを入れてOKなのはどういう条件なのか。お肉を触った箸で生野菜を触るのはNGで、野菜から先の場合は大丈夫、とか。料理の工程については意識して教えるようにしてきました。それが結果的に、片づけを楽にするということを覚えてもらいたくて」
機会が多いことが大事。忙しくてもこどもと料理を続けられる、時短テクとは?

最近はお子さん二人とも、塾や習い事に忙しいそうですが、時間のあるときにはなるべく一緒に料理を作るようにしているというkayoさん。
「パンを焼いたり、おやつを作ったりすることが多いですね。パッと一緒に作れるように、あらかじめ事前に量った粉類を、内容別に袋に詰めて野菜室に入れてあるんです。料理って、レシピを見て何グラムとか最初に量るのが手間ですよね。袋詰めの粉類があれば、あとは卵や豆乳などの液体分だけを混ぜるだけ。スコーン、ホットケーキ、クッキー用の粉類をよくストックしています。あとは米粉パン、蒸しパン……など、粉から作るお菓子はすぐ作れる用意をしています」
ストックはいつも4袋くらいを目安に作るそう。
「何かを作ろうと思い立ったら、一気に4倍の量の粉を用意して、4等分に。袋に分けておけば、あと3回は楽ができるんです。繰り返し作ることで、量も自然と覚えますし、レシピを見なくても焼き上がります」
お菓子作りのあるある悩み「お菓子の型」の収納にも一工夫

お菓子作りのお悩みとしてよく挙がるのが、スタッキングしづらいクッキー型やケーキの型などの収納のお悩み。kayoさんはどうしているのでしょうか?
「型類はヴィンテージの丸い缶にまとめて、キッチンではなくリビングのチェストに収納しています。便利グッズが無限にある調理道具も、なくてもなんとかなりそうだなと思うものは、なるべく手を出さないように気をつけています」

Kayoさん宅のリビングの主役がこちら、印象的なアンティークのカップボード。「ERCOL」のもので、大阪のアンティークショップで見つけたお気に入りだそうです。

中には、カトラリーや、レッスンで使用する器、かご類が整理されています。お料理教室で使用する食器や、上で紹介した型類もここに収納。キッチンで使うものはキッチンに、と頑なにならず、流動的な収納が素敵です。
『簡単で、作り続けられること』が手づくりのお菓子を作り続けるためのコツ

こどもたちのおやつは、基本的に手づくり。ふだんの買い物でも、市販のお菓子を買うことはないそう。
「毎日焼きたてというわけではなくて、焼き菓子をストックしておくとか、冷凍しておいたものをリベイクするとか。作っておいたグラノーラにフルーツを添えて、ヨーグルトをかけて終わり、とか。市販のものがダメというよりも、おやつは家で用意できるから、買う必要がない、という感じですね。もちろん、こどもたちは、お友達の家などで市販のお菓子をいただいたときは、なんでも食べています。わが家は外食も大好きですし、無理をしすぎないことは心がけています」

こどもたちとのおやつタイムは、ほっとする時間。ゆっくりお茶をしながら、自然と会話も弾みます。
「料理って、『簡単で、作り続けられること』が一番。なるべく作る人の負担を減らすこと、そのために何ができるのかなということを、いつも考えています。こどもたちにも、手づくりって思ったより簡単だな、楽しいな、と思ってもらえたら、うれしいですね」

料理家として、母として、さまざまな工夫をこらしながら、こどもたちに無理なく料理の楽しさを伝えているkayoさん。お話からは、キッチンが単なる調理の場ではなく、コミュニケーションや学びの場でもあることを改めて感じることができました。