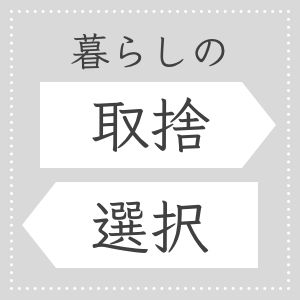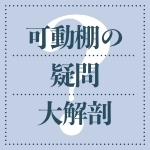長男が関東の「御三家」と呼ばれるトップクラスの私立中学校に合格したMさん。小学生の次男と長女も、兄に憧れて中学受験に挑戦する予定です。Mさん宅では長男の受験期間中から、きょうだいみんながリビングで学習しています。今回はリビング学習のための空間づくりと、性別の異なるきょうだいの収納ルールについて聞きました。
なるべく勝手に片づけない。こどもと意見交換しながら地道に片づけ

関東の某市で代々クリニックを営むMさん(ママは40代)邸は、最寄り駅から徒歩10分ほど、築5年の注文住宅。1階はクリニック、2階が自宅です。18畳のLDKと14畳のこども部屋は一続きで、引き戸で仕切れるようになっているため、かなり広く感じられます。キッチンとパントリーも、玄関からの階段踊り場に続く回遊式構造になっているので、家事動線はとてもスムーズ。余計なモノもほとんどなく、かなりの収納上級者とお見受けしました。
「わが家は中学生の長男、中学受験に挑む小学生の次男、まだ塾に通う前の小学生の長女の3人きょうだい。全員それぞれ個性的で好みも異なるので、毎日片づけについての口論は絶えません。私は片づけたい、でもこどもたちはそれぞれ『まだ使ってる』。そう言いつつも使わずに出しっぱなしにしていることも多いので、困ることもあります。でもなるべく勝手に片づけず、きちんと話し合うことを心がけていますね。本人たちの言い分を聞いて、お互いに落としどころを見つければ、なんとか片づいていく。その繰り返しで、正直疲れることもあります(笑)。とはいえ、やっぱり『リビングにはあまりモノがない方が落ち着くね』という意見は共通しているようです」
こども部屋はあるが、リビング学習が中心

こども部屋からリビングを見たところ。こどもたちが幼かったころは、みんなで走り回って遊んでいたそう。
「こども部屋はあるのですが、ダイニングテーブルか、テレビのそばに造作したカウンターテーブルを使って、こどもたちはみんなリビングで学習しています。まだ個室は与えていません。二段ベッドは長男と次男が使っており、長女は私と一緒に寝室で寝ています。特に長男にはそろそろ個室が必要かな、と考えているところ。オンライン英会話などで、どうしても個室が必要なときは、長男は階下のクリニックの部屋を使って集中しています」

本棚は次男と長女の本が中心。低学年の長女は、まだまだおもちゃが大好き。おもちゃ用の収納スペースをあえて設けると部屋が狭くなってしまうので、バケツ型のソフト収納を使って整理をしているそう。
リビング学習をするため、年齢性別の異なるきょうだいのルール

「たまに3人がみんなリビングで集中して勉強するという、奇跡のような日もありますが、そんなことはなかなかなくて(笑)。たとえば以下のようなルールがあります。
・(テスト前など)その時期、一番頑張らなければいけない人が少し離れたカウンターテーブルを使う
これがきょうだい間で自然とルールになりました。ルーティンの勉強をする人は、ダイニングテーブルを使います。
・誰かが勉強している間、ゲームをしたい人は、音を消す
・YouTubeが見たいときはタブレットで
・テレビが観たいときは、寝室の小さなテレビを使う
場所と音に配慮したいろいろなルールがあります。
次男は、長男が受験に挑戦する姿を見てきたのと、いよいよ次の冬は自分の番という緊張感もあるので、このルールを遵守していますが、長女はなかなか(笑)。歳の離れた長男と長女がバチバチになることもあります」
家事や生活も学習の一環に。リビング学習の利点とは?
そうはいっても、リビングでは気が散ってできない…ということもあるのでは?
そう尋ねると、Mさんはリビング学習のメリットについて教えてくれました。
「そうですね、難しいときもありますが、長男の受験を終えてみて、私はリビング学習の良さを実感しました。まず、親からこどもへ声がかけやすという点。本人が煮詰まっていないか、家事をしながら観察しています。時間も決めやすい。まわりも協力するという空気があると、集中しやすいように思えました。また、キッチンが近いので、野菜の断面や食材の産地を確認させたり、湯気や水蒸気の様子を見せるなど、理科に役立つことがたくさんあります。中学受験は机上の勉強だけでなく、そういう生活の情報が役に立つことが非常に多いんですよね」
食事、団欒、勉強。リビングは「フリーアドレス」で

3人のきょうだいが同じスペースでストレスなく過ごすためには、「私物を置きっぱなしにしない」ということが大切だとMさん。オフィスのフリーアドレスのイメージです。
「自分のスペースが決まっていないからこそ、みんなできれいにしておこうという意識を持ってほしいので、根気よく話すようにしています。カウンターデスクやダイニングテーブルの上がすっきりしていれば、やる気も起きると思います。ダイニングは特に、家族全員の食事と団欒の場所でもあるので、何もない状態をキープしておきたいですね」
Mさんは足しげく図書館に通い、こどもたちに役立ちそうな本を借りてきます。これらの本も、テーブルの上に置くのではなく、いつもこども部屋の柱の傍に立てて置いているそう。
「テーブルの上に置いてしまうと、散らかってしまいますし、重ねることで本のタイトルも見づらくなってしまう。とはいえ、本棚を増やしたくありません。そこで、この場所に置くのが習慣になりました。家庭内おすすめ図書コーナーという感じです。しまいこむことがないので、私も返却期限を忘れずに済んでいます」
中学受験をはじめるためには、まず家の中の片づけと、共有スペースをきれいにしておくという意識づけから。そして、毎日の暮らしの中に、勉強に役立つような仕掛けを組み込んでいく。Mさんのおウチづくりには、こどもたちの学習意欲をさりげなく上げる工夫がたくさんありました。
次回は、テキスト管理の方法など、より具体的なテクニックについて紹介する予定です。お楽しみに!