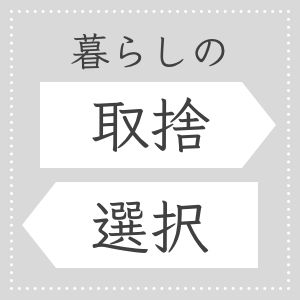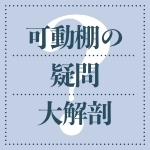スーパーでお買い得のレトルト食品や洗剤が売っていたら、ついついまとめ買いをしてストックしたい(貯めたい)衝動に駆られるもの。しかし、買ったことを忘れてしまい、いつの間にか買ったものが賞味期限切れになっていたり、収納場所を圧迫したりしていませんか?
今回は、そんな不用意な“ロス”を減らせてストック収納の見直しもできる方法とコツを、まとめてご紹介します。
『HOUSTO』厳選!ロスがなくなる“収納の達人”たちのストック収納のルール
目次
ストック収納のコツ①|賞味期限切れをなくすために保存食品の数を把握する(阿部絢子さん)

「ストック収納の食品ロスを防ぐためにも、まずはどんな保存食品をどれだけ持っているのか、把握することから始めましょう」。そう語るのは、生活研究家の阿部絢子(あべ・あやこ)さん。
最初に「①種類ごと(乾物、粉物、茶類、麺類、菓子類)」に分け「お菓子を買いすぎるクセがある」などの失敗パターンを把握し、「②賞味期限」ごとに分けると、“使い忘れ”を防ぐことができるそう。まずはこの2ステップで、ストック収納を見直してみましょう。
阿部絢子さんが『HOUSTO』読者だけに伝授してくれた保存食品の整理収納術が満載の連載記事はこちら
ストック収納のコツ②|取り出しやすさを考えた食品ストックボックスの分類実例(いがりこさん)

「IKEA」の衣類用ボックスを活用してストック食品を4つに分類している、いがりこさん。
各ボックスに余裕があるため、何が入っているか一目で把握でき、使い忘れがなさそうです。また、使用する頻度に合わせてボックスの置き場所をパントリー棚の手前と奥で分けており、サッと取り出しやすい工夫が。奥行きも、有効に活用しています。
いがりこさんのパントリー収納、全貌公開!連載記事はこちら
ストック収納のコツ③|1つのファイルボックスに1種類の日用品。入る分だけをストック(miさん)

ブログ『めがねとかもめと北欧暮らし』が人気のmiさんのストック収納は、土間一箇所に集結し、「1つのファイルボックスに1種類の日用品を収納し、残量が1つになったら引き出す」ルールを設定。
そうすることで無駄買いを防ぎ、ストックの数を家族全員で管理しているそう。ファイルボックスにラベルを貼って中身が一目でわかるようにした工夫も、光ります。
家族全員で協力し合う、miさんの収納ルールをチェック!連載記事はこちら
ストック収納のコツ④|貴重な収納場所を圧迫しないようにネット宅配を利用(春原弥生さん)

縦長狭小一軒家に住む『ズボラ式こそうじ術』(文芸春秋)でお馴染みの春原弥生(すのはら・やよい)さん。
気づけば、ストックの山となっていたおウチ……。収納スペースにも家賃がかかっているという視点で考えたとき、ストック品の「ちょうどいいありかた」とは? ネット宅配を使って買い置きストックを控えたエピソードや、やワゴン収納、お子さんの協力を得るアイデアを、コミックエッセイで今すぐチェック!
春原弥生さんの『ズボラ親子のお片づけ日記』連載記事はこちら
ストック収納のコツ⑤|大切なのはストック場所を明確にすること!

ひとり暮らしや狭小住宅でおウチの収納場所が限られていると、ストックの量が収納量を超えてしまい、はみ出たものをとりあえず適当な場所にしまっているケースが見受けられます。また、家族で買い物を分担しているとストックにダブりが発生し、「急いで消費しないと!」と無理やり理由をつけて消費速度を上げるという本末転倒なことも……。
こういうときは、“あちこち収納”をやめて、決まった「ストック置き場」をつくることが大切。実践してみてくださいね。
「今日からはじめる収納」収納アイデアの連載記事はこちら