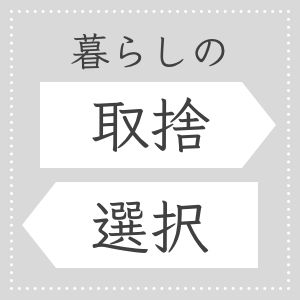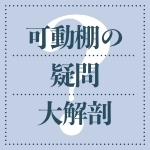すっきりと整った兄弟のこども部屋実例は、思春期のこどもたちを育てる層を中心に、多くの関心が寄せられました。今回は整理収納アドバイザーの要めぐみ先生に、「片づけ教育」についてお話を伺いました。きれいに整ったこども部屋を本人にキープさせる秘訣は、どんなところにあるのでしょうか。
わが家の片づけ教育ヒストリー

こども部屋の片づけは、皆さん頭を抱えることの一つだと思います。私は片づけサポートの現場でめちゃくちゃに散らかったこども部屋をたくさん見てきました(笑)。男の子は特にそうだと思いますが、親が何もせずに片づけを身につけたという子は、ほとんどいないと思います。私も2人の男児子育ての経験から、やはりできるだけ幼いころから片づけへの動機づけをしておくことが大事かな、と考えるようになりました。
そう言うと、「もう手遅れなの!?」と思われるかもしれませんが、思春期だってまだまだ大丈夫。片づけは大人になっても習慣化できるものなので、安心してください。
まずは、わが家の片づけ教育からお話しますね。
どんなに狭くても「こども部屋」を与えることが大切

息子たちは、兄弟でまったく性格が異なります。
4月から高校3年生になる長男はダンス部でおしゃれが大好き。モノに愛着があり、漫画や思い出グッズなど、なんでもとっておきたがるタイプ。一方、4月から中学3年生になる次男はサッカー部に所属。スポーツが大好きで、モノに執着が一切なく潔い性格です。
息子たちが小学生低学年のころは、2人部屋でした。ずっと家族4人、布団で寝ていたのですが、長男はベッドへの憧れを持つようになり、小5のときに「自分の部屋がほしい」と言い出しました。それが、それぞれ4.5畳のこども部屋を与えるきっかけになりました。
こども部屋は、親からすると「何をするかわからない」という不安もありますが、思春期に自分だけの空間を持つことは、こどもの成長と心の安定につながると私は考えています。住宅事情にもよると思いますが、どんなに狭くてもいいのです。
「自分で片づける」をルールにこども部屋を与えました

わが家では、こども部屋を作ったときに、「自分の部屋は自分で片づける」という約束をしました。
そして、毎週日曜日になると小さな袋を渡し、「ここにゴミといらないものを集めて入れておいで」と伝えました。消しゴムのカスや、プリント類、なんでも袋に入れてきたら褒めて、時にはお菓子を買ってあげるなどご褒美をあげることもありました。
モノが停滞していると家の中がよどみます。モノに支配されると暮らしは息苦しくなり、掃除も大変に。そういうことを、肌感覚で教え込みたいと思っていました。
特に長男は使わなくなったおもちゃなどを溜め込んでいたのですが、それがたとえ祖父母に買ってもらったものであっても、「今必要がないものは、いらないもの。手放すことは全然悪いことじゃないよ。でも本当に大切なものだと考えているなら、とっておきなさい」と話し、手放すタイミングはなるべく本人に決めさせるようにしてきました。
「買う」ではなく「買い換える」をキーワードに物量管理

学生の部屋で散らかりがちなのは「プリント類」と「服」だと思います。タブレットが普及したとはいえ、学校からの通達はまだまだ紙。
息子たちには小学生のころから、プリントは
「とにかくクリアファイルに入れて持ち帰るように」と言い聞かせました。自分で仕分けるのはハードルが高いと思いますが、せめてぐちゃぐちゃにならなければ御の字と考えて(笑)。
また増える一方の洋服は、「使わなくなったものをお母さんに持ってきてくれたら新しい服を買いに行こう」というルールに。文房具も同じです。「新しいモデルが出たから買って」ではなく、「買い換える」という発想に。
歯ブラシを探す人はいない。モノの住所感覚を身につけさせる

そして、「すべてのモノに住所をつくる」こと。多少散らかったとしても、戻す場所がわかっていれば、すぐにきれいになります。本人たちにその意識があるようなら、あまりガミガミ言わないようにしてきました。
歯ブラシの置き場所は決まっていますよね? 歯ブラシを探すという人はいないと思います。習慣化された歯磨きのように、片づけをすること。
これらは、2人が幼いころから言い続けてきたことです。
今もたまに試験前など、部屋が散らかることもありますが、基本的には自分で片づけをしています。今回は部屋の撮影があるということで、かなり丁寧に片づけをしていたようですが(笑)。やはり日常から片づける習慣があるから、公開にOKを出すこともできたんじゃないかなと思います。
まずは親が片づける!こどもはリビングの風景をお手本にするもの

振り返ってみれば、息子たちへの「片づけ教育」には6年くらいかかったと思います。やはり一朝一夕でできることではありません。とにかく、根気よく、具体的に言い続けてあげること。そして一番大切なのは、親自身が片づける習慣を背中で見せてあげる、ということです。
まだお子さんが小さいなら、今のうちから親自身が家の中を整える習慣をつけておくといいと思います。きれいなリビングを心がけておくと、こどもたちもそれを当たり前の風景として受け止めます。これは、逆も然り。散らかったリビングが当たり前になれば、こども部屋も散らかりやすくなるのです。
毎日の片づけ習慣を家族で続けながら、こども部屋を与えたはじめのうちは、親が入ってあげて、一緒に片づけを手伝ってもいいと思います。きれいにして気持ちもリフレッシュするという小さな成功体験を積み上げてもらうことが大切です。
そして、もうお子さんが中高生になっている場合。
ぜひ、家の中を見直してみてください。リビングをはじめ、モノが出しっぱなしになっていませんか? こどもが大きくなっているからもう手遅れと考えずに、まずは親から片づけをはじめてみましょう。こどもたちが目にする家の中の風景を整える。こども部屋の改革はそこからです。時間はかかると思います。でも根気よく続ければ、家族で片づけの習慣は身につけることができます。
片づけをすることは、精神的な効果が大きいと思います。部屋がきれいなら、勉強も趣味もやる気がわく。それをこどもたち自身が感じてくれたら自立のスタートです。
将来的に、一人暮らしをしたときにも困らない大人に。そんな頼もしい姿を想像しながら、家族で片づけを楽しんでもらえたらと思います。